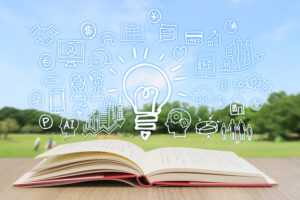2年目社員の座談会 ― 実際の言葉から見えてきた会社にとって大切なこと
本記事は、弊社のクライアント企業で実際に行った企画をもとにしています。入社2年目の社員が集まり、仕事のやりがいや葛藤、成長の実感について率直に語り合いました。
「任された責任に戸惑った」「先輩に助けられた」「今度は自分が後輩を支えたい」「頑張った日のご褒美が力になる」――そんな等身大の言葉には、会社にとって大切なエッセンスが隠れています。
座談会を通して浮かび上がったのは、責任を引き受ける力、学びをつなぐ文化、セルフケアの知恵、そして初心忘るべからずの精神でした。

責任を受け止める姿勢から見えてくること
「最初は『えっ!? 全部任されるの!?』とプレッシャーでした。でも、とりあえずやってみたら、だんだん慣れてきました」「説明会の進行は前日から緊張で眠れなかった。でも“学生のために”と考えたら、不思議と力が出たんです」
これは、採用担当として配属された社員の方が発せられたものです。つい先日まで学生だった彼女は、任された責任に戸惑いながらも、飛び込んでみることで道が開けていく感覚を掴んでいくまでの心の葛藤を感じさせられます。こうした姿は、責任を恐れずに受け止めること自体が成長の原動力になることを教えてくれます。「とりあえずやってみた」という言葉には、若手ならではの力強さが宿っています。責任を前に素直に一歩を踏み出す姿勢こそが、人を育てていくのだと思います。
先輩の言葉を素直に受け止める力
「分からないことは一人で抱え込まず、先輩に聞くことが大事」「1年目のとき先輩に声をかけてもらって救われた。今度は自分が後輩に同じことをしたい」
先輩の言葉をまっすぐに受け止め、それを行動に移していく姿勢が印象的です。そこには、経験の浅さを補って余りある“素直さ”があります。さらに「後輩に返したい」という言葉には、教育の連鎖が芽生えていることが表れています。仕組みや制度だけでなく、人から人へと想いがつながっていく。こうした流れが会社を支える文化になっていくのだと感じます。
こうした文化の醸成の過程が把握できるのが、若手社員を集めて行う座談会のメリットです。
自分を励ます小さな習慣が映すこと
「頑張った日はスタバに寄る」「コンビニでスイーツを買って帰る」
一見ささやかな習慣に見えますが、ここには毎日を前向きに積み重ねていくための知恵が込められています。責任やプレッシャーを抱えながらも、自分を励まし気持ちを切り替える小さな工夫。それがあるからこそ、また明日も挑戦できるのです。
大きな成果だけが人を成長させるわけではありません。こうした日常の習慣が、人を長く、持続的に成長させていく支えになるのだと思います。このような些細な事柄からも、仕事や生活を楽しんでいることが伺えます。同僚や先輩にも響くものがあるのではないでしょうか。
初心忘るべからずを呼び覚ます
「まだまだ分からないことばかり。でも少しは後輩に伝えられることがあると思う」
この控えめな言葉は、若手の成長を示すと同時に、先輩やベテラン社員に自らの原点を思い出させる力を持っています。
誰もがかつては新人であり、支えられながら一歩ずつ成長してきました。その記憶を呼び起こすきっかけを、若手の等身大の言葉が与えてくれるのです。若手を育てる場でありながら、同時に先輩自身が「初心忘るべからず」を思い起こす場にもなっているのだと感じます。
まとめ
2年目社員の座談会で語られた実際の言葉から見えてきたのは、会社にとって本当に大切なことです。
- 責任を引き受け、成長の糧に変えていく力
- 先輩から学び、後輩へと受け継ぐ教育の連鎖
- 日々を前向きにするセルフケアの知恵
- そして、先輩社員に「初心忘るべからず」を呼び起こす力
特別に飾られた言葉ではありません。だからこそ心にまっすぐ届き、読む人を動かします。座談会は単なる若手紹介の場ではなく、会社全体が互いに育ち合う社風を築く仕掛けなのです。