社内報で「創業物語」を伝えるときに気をつけたいこと― “自慢話”にさせず、心を動かすストーリーにするために ―
社内報の企画として「創業者のエピソードを取り上げたい」というご相談をいただくことは少なくありません。
会社の原点を知ることは、社員にとって「今、自分がこの会社で働いている意味」を見つめ直すきっかけになりますし、理念や価値観を伝えるうえでも非常に有効です。しかし一方で、語り方を誤ると、「成功者の自慢話」「昔の苦労話」として受け取られてしまうこともあります。読者が“身内”である社内報だからこそ、創業物語をどのように伝えるかには、特別な工夫と配慮が必要です。
この記事では、私がこれまでに社内報制作に携わる中で得た知見をもとに、“共感される創業ストーリー”の編集ポイントと語りの技術をご紹介します。
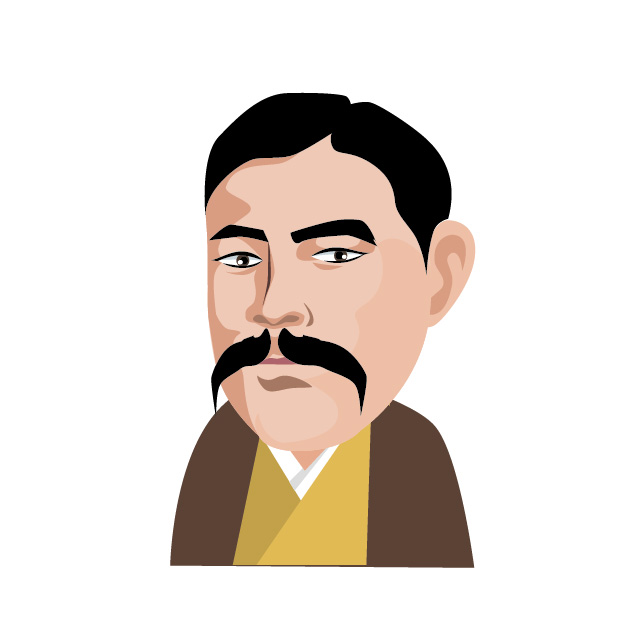
1.社員に“関係ある話”として始める
創業の経緯や当時の苦労をそのまま語っても、今の社員にとって関係が感じられなければ他人事になってしまいます。まずは、「この話は、いまのあなたにもつながっている」という接点づくりが大切です。
たとえば――
「今では当たり前になっている〇〇の仕組みも、実は創業時のある決断がきっかけで生まれました。」
こうした語り出しにするだけで、読者の関心のスイッチが入り、「自分ごと」として読み進めてもらえる可能性が高まります。
2.“苦労話”ではなく、“乗り越えたプロセス”を描く
「資金繰りが大変だった」「人材が集まらなかった」といった創業時の苦労は、多くの企業に共通する話です。しかし重要なのは、“どうやって乗り越えたのか”というプロセスに焦点を当てること。
「信頼を得るために、まずは顔を覚えてもらうことから始めた。毎朝、工場の前に立ち、出勤する人に挨拶を続けた日々が、今の“顔の見える関係”の原点になっています。」
「経験」と「今の価値観」が結びついていることがわかる構成にすることで、社員は自然と納得感を得ることができます。
3.“支えてくれた人”に光を当てる
創業者が「すべて自分の力で成し遂げた」と語ってしまうと、どうしても“自慢話”に聞こえがちです。
むしろ、誰かに支えられ、助けられながら歩んできた姿を描くことで、読者の共感は深まります。
「仕事もなく、気持ちが沈んでいたときに、“一緒にやろうよ”と声をかけてくれたのが、今の取引先のAさんでした。あの一言がなければ、会社は続いていなかったかもしれません。」
“人とのつながり”を描くことで、会社の文化や価値観の深みが自然と伝わります。
4.“今の私たち”につながるストーリーにする
創業者の経験や想いを語るときは、それが今の制度・文化・考え方にどう息づいているかまで示すことが重要です。
「“現場の声を第一に”という姿勢は、創業当時、直接お客様からクレームを受けながら商品改善を繰り返した経験から始まっています。」
社員が「その想いをいま自分たちが受け継いでいる」と実感できると、過去の物語は会社の“生きた文化”として機能するようになります。
5.“弱さ”を語ることで共感が生まれる
そして、創業物語において最も大切なのは、創業者自身の“弱さ”をどこまで語れるかです。
不安、迷い、葛藤――それらをあえて隠さずに語ることで、社員は「完璧な人が作った会社」ではなく、「人間らしい感情と決断の積み重ねで築かれた会社」だと感じられるようになります。
「最初の社員を迎えた夜、“この人の生活を自分が背負えるのか”という思いに押しつぶされそうになりました。正直、怖かった。けれど、それでも逃げなかったことが、自分にとっての第一歩でした。」
こうした心のざわつきや、忸怩たる思いを飾らずに語る姿勢にこそ、社員の心が動くのです。
6.感動を“演出”しない。けれど心が動くストーリーにする
創業ストーリーでありがちなのが、“感動”を無理に演出しようとすること。
涙を誘うエピソードや成功体験の美談を並べすぎると、かえって白々しく感じられる危険があります。
実はここが、最も注意すべき“感情の境界線”かもしれません。作られすぎた物語や、よく練られたエピソードは、ときに読者を冷めさせてしまうのです。それがたとえ事実であったとしても、「いかにも“語るために整えられた話”」と感じられてしまえば、社員の心には届きません。読者が求めているのは、「すごい話」ではなく、「等身大の、誠実な記憶」です。
必要なのは、感動を狙うのではなく、実感のある言葉で語ること。
たとえば――
「会社に行くのが怖かった日もありました。
やるべきことは山ほどあるのに、何をしていいかわからず、車の中で缶コーヒーを片手にぼんやりしていた時間の方が長かったかもしれません。」
このように、心のざわつきとともに浮かび上がる日常の情景を、そのまま描写する。大げさな説明も脚色もいりません。その“呼吸のまま”の言葉にこそ、読者の心は静かに動かされます。
感動は演出するものではなく、にじみ出るもの。読み手が「これは、自分のことかもしれない」と思える瞬間に、社内報は“語り”から“共有”へと変わるのです。
7.社員の声を添えて“対話型の物語”にする
創業者の語りだけで完結させずに、社員の声や受け止め方を添えることで、ストーリーが“対話”へと昇華します。
「創業者の話を聞いて、何かを始める勇気をもらいました」
「あの時代の話が、今のこの制度に繋がっていると思うと、日々の仕事の見方が変わりました」
こうしたコメントは、読者の視点を代弁してくれるだけでなく、会社の一体感を生み出す装置にもなります。
■おわりに
創業物語は、単なる過去の出来事ではなく、企業の“精神的な資産”です。ただし、それを“感動的な美談”として語るのではなく、誠実な実感として社員に届けることが、社内報における最大のポイントです。
過去と現在、そして未来をつなぐ――
創業エピソードこそが、社員と会社の心を結ぶ“静かな橋”になり得ます。
※この記事は、社内報の制作を担当する広報・総務・人事の方、または経営者・創業者ご本人向けに執筆しています。御社らしい「創業の物語」が、社員の心に届く一編となることを願って――。
新卒の定着率アップに社内報を活用しませんか
・・・その答え、社内報が変えてみせます!
採用ご担当者様
貴社の新卒採用は順調でしょうか?
「内定者フォローを強化したい」「せっかく採用した新卒が定着しない」・・・そんなお悩みをお持ちではありませんか?
入社後のギャップ、職場の雰囲気、成長の実感・・・新卒が定着しない理由は様々ですが、“伝え方”次第で変えられます。社内報を活用すれば、「働くイメージ」「チームの一体感」「未来への期待」を育み、新卒が「ここで働き続けたい」と思える環境を作ることができます。実は、社内報ほど可能性に満ちていながら、活用されていないツールはありません。ぜひ、採用活動に社内報を取り入れてみませんか?



