語りのそばに立つということ〜社内報担当者のための「語りを受け止める10の心得」〜
語りを編む人の静かな覚悟
社内報の取材や編集をしていると、ときに迷いが生まれます。
「この話を、どう伝えればよいのだろう」
「本音を話してくれているだろうか」
「この人の言葉を、ちゃんと受け止められているだろうか」
社員の語りに触れるということは、その人の人生の一部に立ち会うことです。だからこそ、私たちはただの聞き手や記録者ではなく、“語りのそばに立つ編集者”でありたい。語り手のリズムを尊重し、想いの奥に耳を澄ませ、語られた言葉にそっと手を添える存在でありたい。そんな静かな覚悟を胸に、ここでは「語りを受け止めるための10の心得」を、実践とまなざしの両面から紐解いていきます。
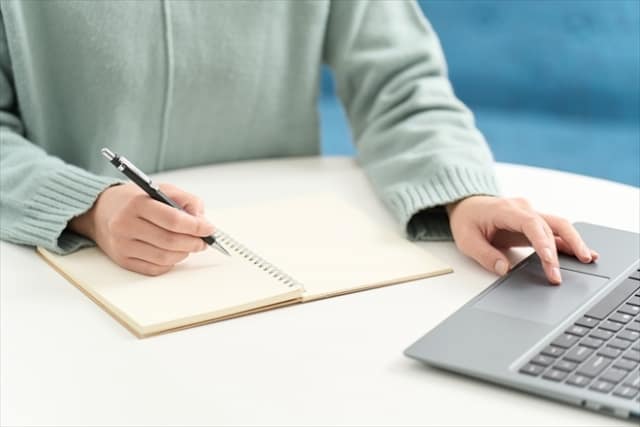
語りを受け止める編集者の心得10カ条
社員の語りを記事として届ける際、編集者やインタビュアーには言葉を整える以前に、“どう向き合うか”という姿勢が求められます。
語り手が安心して話せる空気をつくり、その人の経験や感情を丁寧に受け止め、必要に応じて希望や意味をともなう形で言葉にしていく──。
この10カ条は、そうした関わりを実現するための“心の指針”です。書く技術ではなく、語り手のそばに立つ覚悟とまなざしを育てるために、大切にしたいスタンスを整理しました。
1.評価せず、まず受け止める
語り手の言葉が、愚痴のように聞こえたとしても、それをすぐに否定したり判断したりするのではなく、「そう感じたんですね」と一度まるごと受け止めてみること。それだけで、語り手は安心し、自分の言葉を少しずつ深めていけます。
2.答えを急がず、沈黙にも意味を見出す
沈黙は、語り手が何かを言葉にしようと格闘している時間です。その間を遮らずに待つこと、相手の考えが言葉になるのを信じて見守ること。それが、深い語りを生む“静かな対話”になります。
3.相手のペースを尊重する
話すスピードも、言葉の出方も、人によって異なります。編集者の役割は、自分のテンポで話を引き出すことではなく、相手の呼吸に合わせて寄り添うこと。話したくなる“間”を大切にして、共に流れをつくっていきましょう。
4.出来事よりも、その人の“感じたこと”を大切にする
何が起こったか以上に大切なのは、その出来事をどう受け止めたか、どんな気持ちが動いたかということ。その人らしさや、価値観が浮かび上がるのは、事実ではなく“感情の記憶”です。
5.書き手ではなく、“語り手の伴走者”として関わる
編集者が主役になってしまっては、語りの意味が失われてしまいます。私たちは、語り手が自分の言葉を探す旅に並走する伴走者。問いを投げ、うなずき、時に背中を押す──そんな在り方が、信頼を育てる土台になります。
6.愚痴の中にも希望の芽を探す
「もう限界です」「なんで私ばかり」──そうした言葉の中にも、「本当はこうなってほしい」という願いが隠れています。その“芽”を見つけて言葉にしていくことが、語りを希望の物語へと変える第一歩です。
7.誰か一人の語りが、組織にとっての資産になると信じる
語り手がどんな立場であれ、その人の言葉には、必ず誰かの心に響く力があります。目の前の語りが、別の誰かの背中を押し、部署の壁を越えて共感の連鎖を生み出す──その可能性を信じることが、社内報を文化へと育てます。
8.言葉を整える前に、想いを尊重する
編集の作業に入ると、“美しい文章”をつくろうとしてしまいがちです。けれども、それより先にすべきなのは、「この人は何を伝えたかったのか?」という想いへのリスペクト。整える前に、受け止める。順番が大切です。
9.目の前の語りが、組織の未来とつながっていると意識する
語りは個人のものにとどまらず、読み手の行動や組織の文化に波紋を広げます。たとえ現場の一コマであっても、「これは未来の誰かにとってのヒントになるかもしれない」と思って向き合うことで、言葉の選び方は変わります。
10.「話してよかった」と思ってもらえる関わり方をする
最終的に記事にならなかったとしても、語り手が「話してよかった」と思ってくれたなら、それはすでに社内報としての価値が生まれています。言葉を拾うことよりも、関係をつくること。それが、語りの文化の土台となります。
語りを通して、人と組織をつなぐ
語りを受け止めるとは、目に見える成果や数字のためではなく、人と人との間に“通い合うもの”を育てていく営みです。その姿勢があるからこそ、語り手は言葉を差し出し、編集者はそれを未来につながるかたちで届けることができるのです。
社内報担当者は、“書く人”である前に、“聴く人”であり、“信じる人”であること。その静かな覚悟とともに、語りのそばに立ち続けていきましょう。



